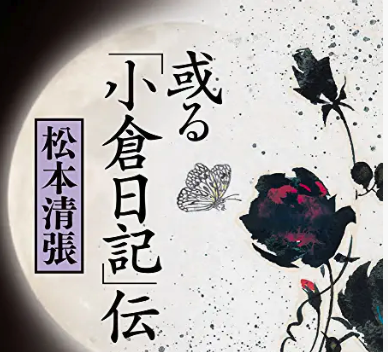このところ小説への少し熱い思いが湧き上がっている。老後の時間をいかに有効に使うかということをふと思う時があり、読書ひいては小説などを読むあるいは書くことが時間を費やす良き対象になるのかもしれないとの認識がある。
自己啓発本や歴史物などノンフィクションはそれなりに読んできたが、小説、しかも著名な名作というものをあまり読んでいないことに以前から劣等感ほどでなくとも多少の後ろめたさみたいなものを感じるのだった。
死がどんどん身近に具体的になりつつある老境の入口にあって、このところ毎日のように死のことを考えるのだった。死の恐怖を逃れるためにも小説世界には何らかの救いがあるように思えてならない。小説という虚構の世界に死を乗り越える何かがないだろうか、というところであろう。
前置きが長くなったが、最近読んだ本に関してここに備忘録メモとして感じたことなどを記載しておこうと思う。初回の今回は松本清張「ある「小倉日記」伝」である。松本清張の芥川賞受賞作。松本清張と芥川賞というのは少しばかり違和感ある。それも含めて、巨匠のデビュー間もない初期の作品がどんなものだったのか、図書館で思わず手に取ってしまった。
読んでみて初めて知ったことだが、小倉日記というのは森鴎外が北九州の小倉に軍医として赴任した数年間に記した日記のことだった。だが、主人公は小倉在住で身体に障害のある若者であり、森鴎外の小倉日記について調べ上げて世に残すまでの短い物語なのだ。
松本清張の小説の主人公はたいていが世の中一般から阻害されたり取り残されたりする劣等感や何らかのマイナスの精神構造を有する者であるようだ。その負の情念やエネルギーが時に市井の人には決してできないことを成し遂げることになる。
プラス側の大偉業にせよマイナス側の犯罪にせよ後世の記憶に残るような大事を成すには個人の内的なエネルギーが必須の要素となる。それは野心や憧憬であったり、嫉妬や憎しみであったりとさまざまだが心に占める強い情念に変わりはない。
この「ある「小倉日記」伝」のよいところは、そんなに大それたことを扱ってはいないながら、一部の専門分野では非常に有意義なことをこつこつと成し遂げたことをさらりと記述している体を成していることだ。
実在の人物のお話のようだが作者の松本清張はよく調べ上げたのだと思われる。玄人好みの渋い設定ながら、そこに人間の強い心の存在がしっかり抉り出されている。松本清張のその後の小説テーマの根幹の片鱗が初期の時代の作品からよく読み取れると思われる。